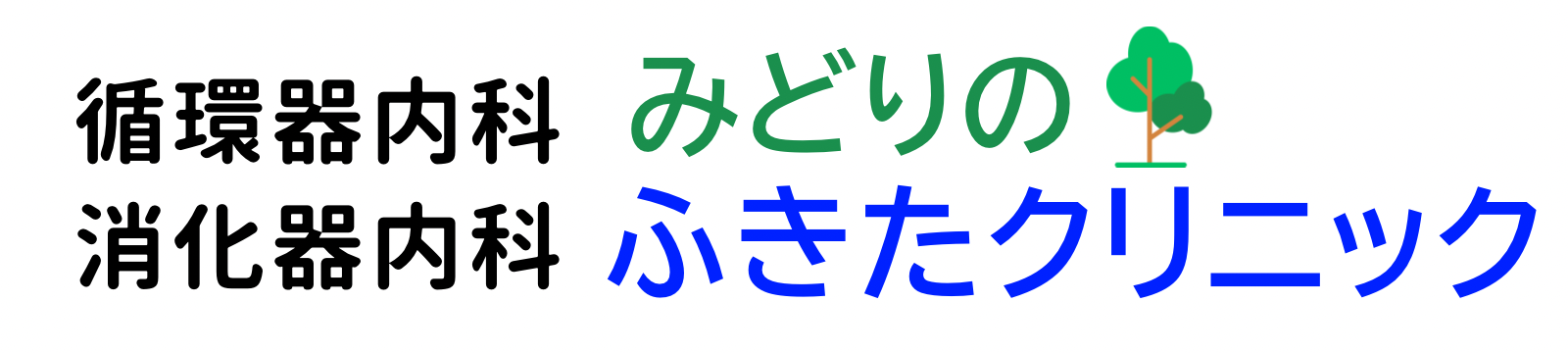血圧が高いと健診で言われたことがある方もいると思います。そして血圧が高くて症状がある方は多くないため、なぜ治療しなければならないのか?と率直に感じられている方も多いと思います。
今回は、なぜ高血圧は治療をしなければならないのか?を含めて、高血圧についてご説明したいと思います。
高血圧
高血圧とは生活習慣病の一種で血圧が高い状態のことです。
では血圧が高いとはなんでしょうか。血圧とは全身の血管が受けている圧です。血圧は2種類あり、血管が受ける圧は心臓が1回ドクンとする間に、一番強いときと一番弱いときです。それがそれぞれ収縮期血圧(一番高い)と拡張期血圧(一番低い)といいます。
日本高血圧学会のYouTubeがわかりやすくおすすめです。
より詳しく言うと心臓から全身に血液を送りだすときに最も強い圧がかかった時(収縮期血圧)と、心臓が拡張し、ふくらんだ大血管が収縮し全身に送り出した時の圧(拡張期血圧)です。
多少血圧が高くても症状はあまりないですが、動画でも触れれれているように放置することで大きなリスクがあります。
高血圧の定義
現在のガイドラインでは診察室血圧140/90mmHg以上を高血圧です。高血圧は潜在的に抱えている方が多く日本には約4300万人の患者さんがいると推計されています。
高血圧の数値の根拠となるのはさまざまな研究です。久山町研究で、収縮期血圧が120mmHg未満、拡張血圧が80mm未満が最も脳心血管病の累積死亡率が少なく、高齢者でも140mmHg以上(90mmHg)以上はそれ以下と比較して優位に脳心血管病のリスクが高いと報告されました。
また、NIPPONDATA80においても、同様に140/90mmHg以上での脳心血管病死亡率の上昇を認めてます。そういった研究をもとに高血圧の定義が定められているわけです。
また、病院でだけで高い、白衣高血圧という状態もあり自宅での血圧の測定が大切です。

高血圧を治療する目的
血圧が高いことでは多くの人は症状がありません。そのため放っておきがちです。しかし、血圧が高いことで今は良くても10年後のような未来に大きな病気を発症したり、リスクをはらむことになります。
なぜなら、高血圧により動脈硬化が進行して脳卒中や心筋梗塞などの心臓病、慢性腎臓不全など重大な病気になる危険性が高まるからです。これが高血圧がサイレントキラー(静かなる殺人者)と呼ばれる所以です。
また、高血圧がある方には脂肪肝があったり、脂質異常症があったり、糖尿病があったりと合わせて病気があることもあります。
血圧の治療の目標
では血圧はどこまで下げればいいのでしょうか。
一般的な治療の目標として、75歳未満は診察室血圧で130/80mmHg未満を、75歳以上では140/90mmHg未満を目指します。
しかし、合併している病気の状態などによっては、より厳格に下げたほうがよい場合や逆に慎重に下げたほうがよい場合があり、年齢によっても目標値が違います。そのためそれらを考慮しながら患者さんごとに目標を設定します。
また、最近のアメリカでの研究では140以下よりも120程度までさらに厳格に下げた方がより脳卒中、急性冠症候群、心不全、心血管死のリスクが下がるという報告もあり、今後も基準が変わっていく可能性があります。
少なくとも今は下げるほうが良いというトレンドです。
高血圧の方に行う検査は?
高血圧は血圧が高ければすぐに薬を始めれば良いというものではありません。
まずは、家族歴を含めた問診、家庭血圧の確認、生活習慣の確認などを行います。その上で、患者さんの必要性に合わせて行います。そのため、まずは自宅での血圧測定をお願いします。
また、病院で行う検査としては下記があります。
心電図検査
高血圧合併症である心肥大(心臓の筋肉が厚くなること)、心臓の虚血の有無(心臓の筋肉への血流不足)、不整脈(脈の乱れ)などの有無を調べます。
胸部レントゲン検査
胸部をレントゲンで撮影することで、高血圧合併症である心肥大、心不全の有無を調べます。
尿検査
尿検査は一見関係がなさそうですが、高血圧合併症となる腎臓への負担や腎臓病の有無を調べる大切な検査です。
採血検査
高血圧とともに動脈硬化を引き起こす脂質異常症や糖尿病の有無を検査します。また、若い方などは一次性高血圧(生活習慣などが原因ではない)の原因となるホルモン異常を探ります。
そのほかに眼底検査、睡眠時無呼吸症候群の検査、ホルター心電図、腹部エコー、頸動脈エコーなどを行うこともあります。
高血圧の治療
高血圧の治療は血圧を下げる薬の治療と、生活習慣の改善です。
薬物治療(薬による治療)
血圧を下げる薬には
- Ca拮抗薬
- ARB,ACE阻害薬
- β遮断薬
- 少量利尿薬
などをはじめに治療し、自宅の血圧を参考に調整を行います。それぞれの薬にメリット、デメリットがあるため、患者さんの状態に合わせて1つまたは複数を組み合わせて治療を行います。
組み合わせて内服する理由は、血圧の薬は1種類の用量を倍にするより、別の薬を組み合わせたほうが血圧を下げる効果が高いこと、それぞれにメリット、デメリットがあり、デメリットを打ち消すために併用する場合もあります。
生活習慣の改善
また、薬剤治療と同じくらい大切なのは生活習慣の改善です。具体的には
- 減塩(食塩摂取量6g/日未満)
- 肥満の予防や改善(体格指数(BMI)*1 25.0kg/m2未満)
- 節酒(アルコール量で男性20~30mL/日以下*2、 女性10~20mL/日以下)
- 運動(毎日30分以上または週180分以上の運動)
- 食事(野菜や果物、 多価不飽和脂肪酸を積極的に摂取、 飽和脂肪酸・コレステロールを避ける)
- 禁煙(喫煙のほか受動喫煙も避ける)
- ストレスを避ける
です。食事や運動などの生活習慣の改善は血圧だけでなく、糖尿病、高脂血症などの改善にも繋がります。また、生活習慣を改善することで将来的に血圧の薬を減量、中止できる可能性があります。
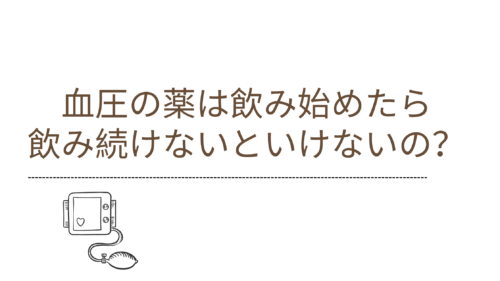
まとめ
血圧は、放っておくことで将来の病気につながる放っておいてはいけない病気です。
当院では療養計画書をもとに、患者さんに繰り返し丁寧に説明をしながら、内服だけではなく、生活習慣の改善も行います。栄養士による栄養指導を実施しています。
高血圧を指摘されたけど病院へ受診してない。。そんな方はぜひ一度病院へ受診することをお勧めします。