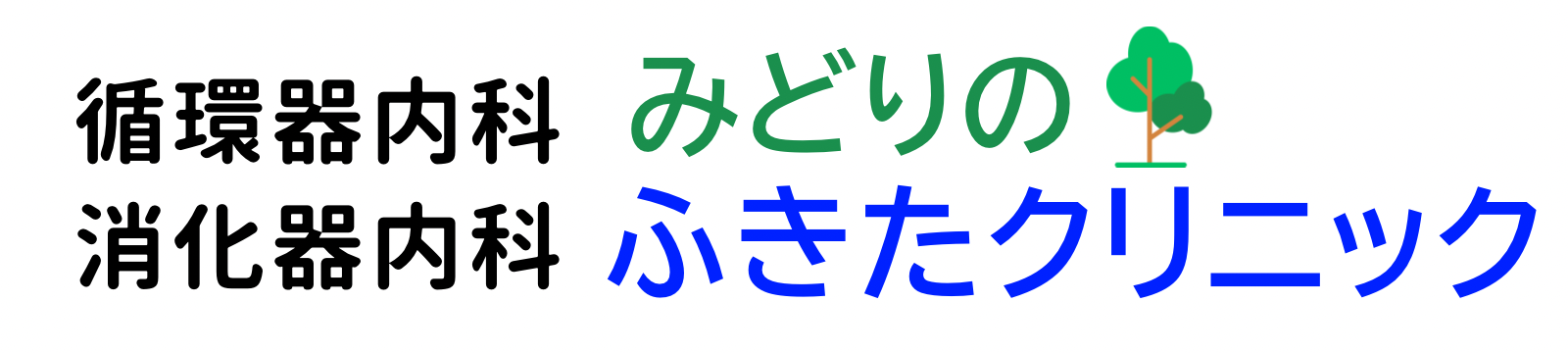お腹の張りや痛み、下痢や便秘が繰り返し起こる病気として知られている過敏性腸症候群ですが、そんな症状が続くと、日常生活にも大きな影響がありますよね。
近年、過敏性腸症候群(IBS)などの症状を和らげる方法として注目されているのが「低FODMAP(フォドマップ)食事法」です。
FODMAPとは、腸で吸収されにくく、大腸で発酵してガスや水分を増やす特定の糖質のこと。これらを減らすことで、お腹の不快感が軽くなる可能性があります。
この記事では、低FODMAP食の基本から実践方法、注意点までを、わかりやすくまとめました。「自分の体に合う食事」を見つけるためのヒントとして、ぜひ参考にしてください。
FODMAPってそもそも何?
FODMAP(フォドマップ)というのは、お腹の中でガスや水分をためやすい成分のことです。名前はちょっと難しいのですが、実は次のような糖の仲間をまとめた呼び方です。
- オリゴ糖(玉ねぎ・にんにく・小麦などに多い)
- 二糖類(牛乳やヨーグルトの乳糖)
- 単糖類(果物の果糖)
- ポリオール(りんごや梨、人工甘味料のソルビトールなど)
これらは小腸でうまく吸収されにくく、大腸まで届くと腸内の細菌に分解されてガスが発生したり、水分を引き寄せたりします。その結果、お腹が張ったり、ゴロゴロしたり、下痢や便秘の原因になることがあります。
どうして注目されているの?
「低FODMAP食事法」は、このFODMAPを多く含む食品をしばらく避けて、お腹の不調が和らぐかどうかを試す方法です。
特に過敏性腸症候群(IBS)と呼ばれる、腸の壁などに直接の異常がないにもかかわらず、長年にわたり腹痛やお腹の張り、便通異常が続く病気で効果があることが、世界中の研究で確かめられています。
オーストラリアのモナシュ大学が行った研究では、低FODMAP食を行った人の多くで腹痛やお腹の張りが減ったと報告されています(Staudacher HMら, Gut. 2014; DOI: 10.1136/gutjnl-2014-307264)。
高FODMAPを減らすとなぜ腹部症状が減る可能性があるのか?
ではなぜ、高FODMAPを減らすとお腹の症状が減る可能性があるのでしょうか?下記のような理由があると言われています。
1. 小腸で吸収されにくい糖質を減らす
高FODMAP食品に含まれる糖(フルクタン、乳糖、果糖、ポリオールなど)は、小腸での吸収が不完全です。吸収されない糖は大腸まで届きます。そのため、2の理由につながります。
Staudacher HM et al., Gut, 2014(DOI: 10.1136/gutjnl-2014-307264)の研究では、低FODMAP食を摂取した群で、小腸での糖質負荷が減り、大腸への到達量が減少していました。
2. 大腸での発酵とガス産生を抑える
大腸に届いた未消化の糖質は、腸内細菌によって発酵されます。その結果、二酸化炭素・メタン・水素といったガスが発生します。ガスは腸を膨らませ、腹部膨満感や痛みの原因となります。
Ong DK et al., J Gastroenterol Hepatol, 2010(DOI: 10.1111/j.1440-1746.2010.06370.x)では、低FODMAP食で呼気中水素ガスの量が有意に減少しました。
3. 浸透圧による腸内の水分増加を防ぐ
FODMAPは水を引き寄せる性質(浸透圧効果)があります。高FODMAPを摂ると、小腸や大腸内に水分が増え、下痢や軟便の原因になります。
これを減らすことで、便通が安定しやすくなります。
Barrett JS et al., J Am Diet Assoc, 2009(DOI: 10.1016/j.jada.2009.07.011)で、フルクタンやポリオールを含む食品摂取後に小腸内の水分量が増加することが示されています。
4. 過敏性腸症候群(IBS)の症状悪化トリガーを減らす
IBSの患者さんは、腸の知覚過敏(通常より腸の膨らみに敏感)があるため、少しのガスや水分増加でも痛みや張りを感じやすいと考えられます。低FODMAP食は、この「膨張の原因」を減らすことで症状を和らげます。
Halmos EP et al., Gastroenterology, 2014(DOI: 10.1053/j.gastro.2013.09.046)で、低FODMAP食によりIBS患者の腹部症状スコアが有意に改善しました。
FODMAP食事法の進め方
低FODMAP食は、3つのステップで行う方法があります。
低FODMAP食事法の進め方
低FODMAP食は、大きく3つの段階に分けて行うのが一般的です。
これはオーストラリア・モナシュ大学が提唱し、多くの消化器専門医や管理栄養士が推奨している方法です(Staudacher HM et al., Gut, 2014; DOI: 10.1136/gutjnl-2014-307264)。
1. 制限期(約4〜6週間)
- 目的:お腹の不調(腹痛、張り、下痢、便秘)の原因となっている可能性のある高FODMAP食品を、いったんほぼすべて避けます。
- ポイント:
- 玉ねぎ、にんにく、小麦、乳糖を含む乳製品、りんごや梨などは控えます
- 米、そば(十割)、鶏肉、魚、卵、低FODMAP野菜や果物を中心にメニューを組みます
- 注意:4〜6週間以上続けると栄養が偏ったり、腸内の善玉菌が減る可能性があるため、期間を守ることが大切です。
2. 再導入期
- 目的:避けていた食品を1つずつ戻し、「どれが自分にとって不調の原因か」を見極めます。
- やり方:
- 1種類の食品を少量から試す
- 2〜3日間お腹の調子を観察
- 問題なければ量を増やす、または次の食品に進む
- 例:乳製品から始めて反応がなければ、次に小麦製品、その次に果物…という順で進める
- コツ:食品を戻す順番は管理栄養士や医師と相談するとスムーズです。
3. 維持期
- 目的:自分にとって食べても大丈夫な食品と、避けたほうがよい食品を明確にして、無理なく続けられる食事に落とし込みます。
- 結果:
- 完全な制限食ではなく、「自分だけの低FODMAP食」が完成
- 好きな食事も楽しみながら症状をコントロールできます
どんな食品が高FODMAP?低FODMAP?
では実際にどんな食材がそれらに含まれるのでしょうか?
高FODMAP(避けたい食品の例)
高FODMAPの食品は糖を多く含む食材が含まれます。具体的には下記のようなものです。
肉類はタンパク質がおおいため、基本的に含まれませんが、ソーセージなどの加工肉は高FODMAPの調味料が含まれることがあるため注意が必要です。
| カテゴリ | 食品例 | 主な理由 |
|---|---|---|
| 野菜 | 玉ねぎ、にんにく、長ねぎ、アスパラガス、カリフラワー、ブロッコリー(茎や花蕾)、芽キャベツ、とうもろこし | フルクタンやマンニトールが多く、ガスや水分を増やしやすい |
| 果物 | りんご、梨、すいか、柿、マンゴー、さくらんぼ、プラム、ドライフルーツ(レーズン、デーツなど) | 果糖やソルビトールが多く吸収されにくい |
| 穀類 | 小麦パン、うどん、パスタ、ラーメン、菓子パン、クラッカー、餃子の皮、春巻きの皮 | 小麦に含まれるフルクタンが多い |
| 豆類 | レンズ豆、ひよこ豆、インゲン豆、あずき(大量)、黒豆(大量) | ガラクトオリゴ糖が多い |
| 乳製品 | 牛乳、ヨーグルト(乳糖あり)、カッテージチーズ、リコッタチーズ、ソフトクリーム | 乳糖が多い |
| 甘味料 | はちみつ、高果糖コーンシロップ、人工甘味料(ソルビトール、マンニトール、キシリトール) | 高濃度の果糖やポリオールを含む |
低FODMAP(食べやすい食品の例)
では低FODMAPはどんな食材でしょうか?
イメージとしては甘くない(糖分がすくない)ものと考えれば良いです。また、小麦粉は高FODMAPですが、穀物は低FODMAPであるため、日本食をイメージすると少しわかりやすいかもしれません。
| カテゴリ | 食品例 |
|---|---|
| 野菜(適量でOK) | にんじん、きゅうり、トマト、なす、ピーマン、ほうれん草(ゆで)、レタス、小松菜、もやし(緑豆)、かぼちゃ(少量) |
| 果物(1食100g程度まで) | バナナ(やや青め)、いちご、ブルーベリー、キウイフルーツ、みかん、ぶどう(少量) |
| 穀類 | 白米、玄米、もち、そば(十割)、グルテンフリーパスタ、米粉パン、オートミール(少量) |
| たんぱく質 | 鶏肉、豚肉、牛肉、魚全般、卵、豆腐、厚揚げ、油揚げ(※ただし、加工肉は除く) |
| 乳製品 | ラクトースフリー牛乳、硬めのチーズ(チェダー・パルメザン)、バター |
| その他 | しょうゆ、みそ(添加物少なめ)、オリーブオイル、ごま油、海苔、わかめ、昆布、砂糖(上白糖・きび砂糖) |
行うにあたり注意すること
低FODMAP食は、長く続けると腸内の善玉菌が減ったり、栄養が偏ったりする可能性があります。また、それ以外の栄養素については考慮していないため、たとえば高血圧の方では塩分過多になるなどの影響がある可能性があります。
そのため、自己流で長期間続けるのではなく、疑問点があれば医師や管理栄養士と相談しながら行うことが大切です。
また、高FODMAPの食事は全員に悪いわけではありません。症状がない人が制限してもメリットは少ないと考えられています。
まとめ
低FODMAP食は、IBS症状の緩和に強く支持される食事法であり、ネットワークメタ分析でも高い効果が示されています。一方で、腸内環境や栄養への影響もあるため、制限期を短く抑え、再導入や維持期で個別調整することが鍵となります。
特に、自分の反応を観察しながら調整していけるスタイルは、長く続ける上でも現実的です。
今後の研究では、腸内フローラの変化やプロバイオティクス併用の効果、アジア圏(日本を含む)における日本食との関係性なども注目されています。
自費診療ですが、MicroBio Meという、飲料メーカーのKIRINが提供している腸内細菌自体を腸内細菌の潜在能力レベルまで見る検査もあり、それらが参考になる可能性もあります。
ご興味がある方は参考にしてみてください。
参考文献:
- Halmos EP, Christophersen CT, Bird AR, Shepherd SJ, Gibson PR, Muir JG. Diets that differ in their FODMAP content alter the colonic luminal microenvironment. Gut. 2015 Jan;64(1):93-100. doi: 10.1136/gutjnl-2014-307264. Epub 2014 Jul 12. PMID: 25016597.
- https://hc.mt-pharma.co.jp/site_cerekinon/self-medication/dietary-cure/article/about-fodmap.html