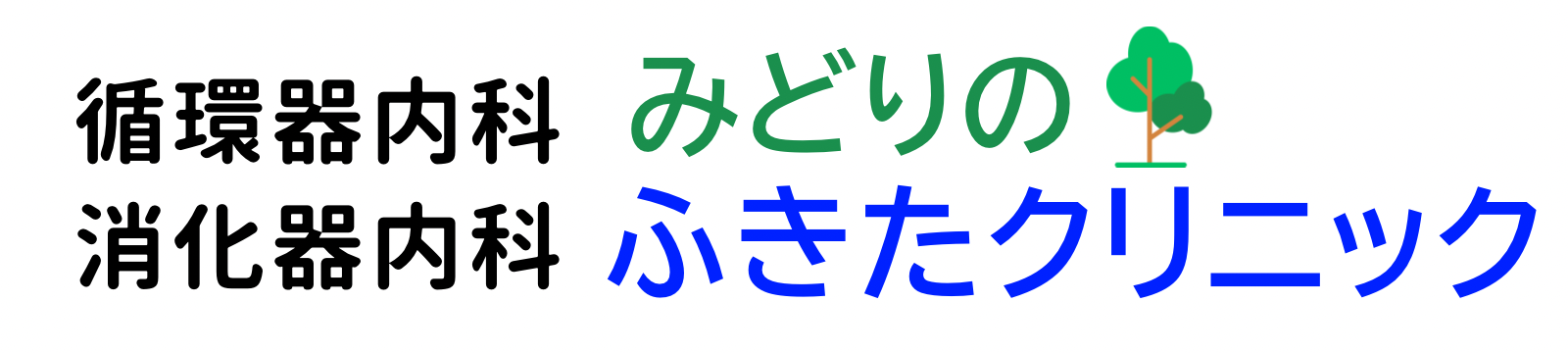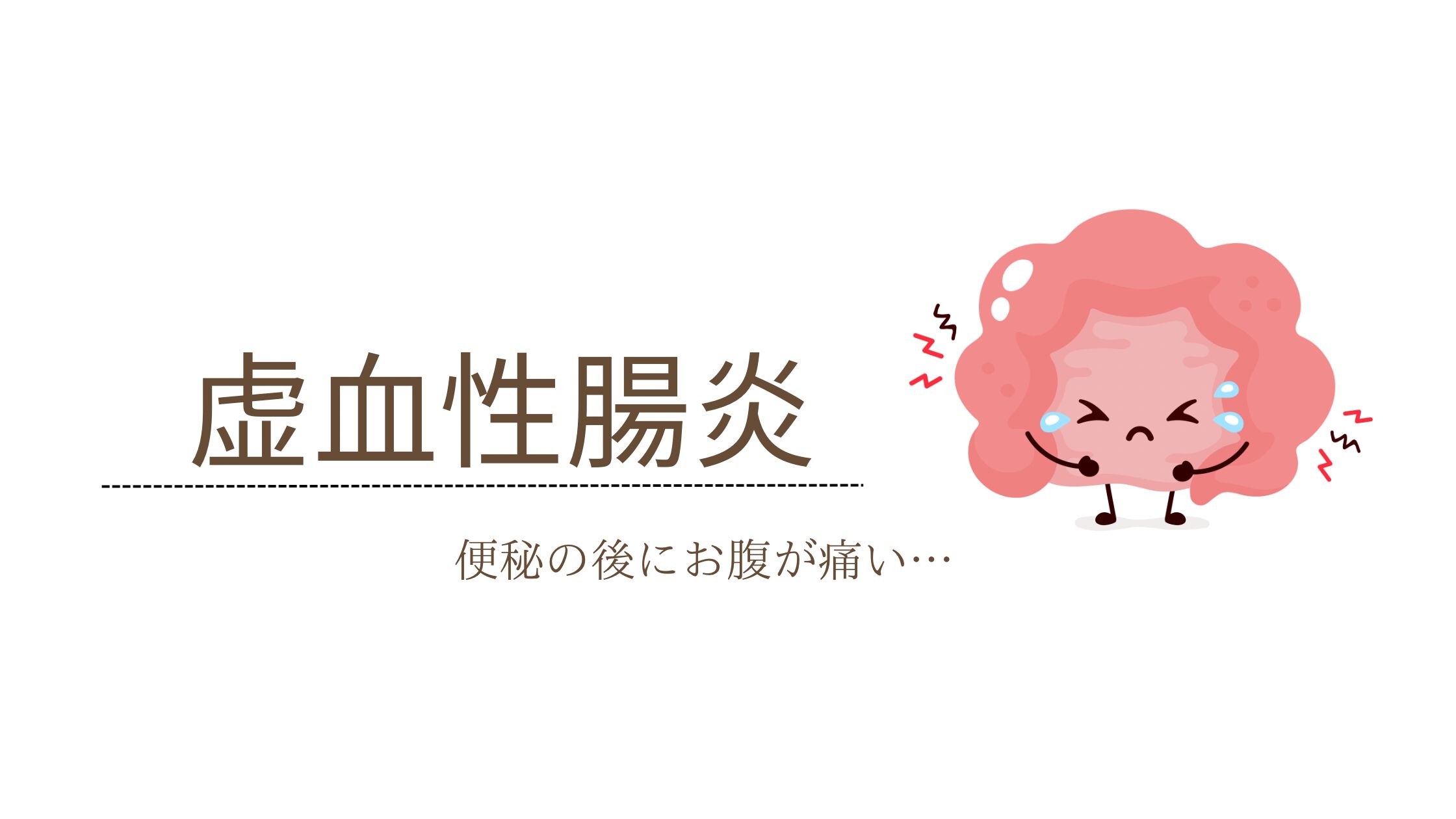虚血性大腸炎とは?
虚血性大腸炎(きょけつせいだいちょうえん)とは、腹痛と血便を伴う大腸の炎症です。
原因としては大腸の血流が一時的に低下することで、腸の粘膜が炎症を起こし、腹痛や血便を引き起こす病気で、特に高齢者や便秘がちの方に多くみられるのが特徴です。
虚血性腸炎は多くの場合は自然に回復しますが、重症化すると腸に壊死や穿孔(穴が開くこと)を引き起こし、手術が必要になることもあります。
今回は虚血性腸炎について一般的な内容を解説します。
虚血性大腸炎の原因
虚血性腸炎の原因はさまざまですが、一般的に便秘など排便との関連が指摘されています。そのほかには
- 動脈硬化による血流障害(加齢・高血圧・糖尿病など)
- 便秘や腫瘍閉塞、浣腸などによる腸内圧の上昇
- 脱水や低血圧による血流低下
- 過度な腹圧(強い咳や重いものを持ち上げる動作など)
- 循環不全をや脱水、出血をきたす原因となる薬剤(降圧薬、ジギタリスなど)
などがあります。これらの原因により大腸に一時的な虚血(血液がうまく届かない)ことで大腸が傷が受けることが原因です。
虚血性大腸炎の症状
虚血性腸炎の典型的な特徴は、
便秘でかなりいきんだ後にお腹が痛くなりそのうちに血便がで始める
です。痛みの場所は左下腹部が多く、下痢症状も伴うこともあります。
症状としては、左〜下腹部の疼痛、血便、下痢などがあります。
虚血性大腸炎の診断方法
虚血性腸炎が疑われる場合、医師は以下の検査を行います。
- 診察と問診
- 腹部エコー(エコーで壁の厚みを見ます)
- 腹部CT検査(腸の炎症や血流障害の確認)
- 大腸内視鏡検査(炎症や出血の部位を特定)
- 血液検査(炎症反応や貧血の有無を確認)
通常は症状の診察と問診で疑うことができます。腹部エコーやCTでS状結腸や下行結腸の壁が厚いことを確認できればさらに診断につながります。
すぐに大腸カメラを行うことは少ないですが、大腸がんなどで、閉塞がありそれにより虚血性大腸炎など、他の病気との鑑別には大腸カメラが有用です。
虚血性腸炎が治った後には大腸カメラを行うことが大切です。実際に経験した患者さんでも虚血性大腸炎後に、大腸がんが見つかったという患者さんもいます。
虚血性腸炎の治療方法
虚血性腸炎の治療法は症状のより分かれます。
軽症の場合(自然回復)
多くの患者さんは、数日間の安静と適切な治療で自然に回復します。
- 絶食または消化に良い食事をとる(腸を休ませる)
- 水分補給をしっかり行う
- 点滴による栄養管理(必要に応じて)
- 抗生剤の投与(細菌感染のリスクがある場合)
虚血性腸炎は一時的に腸の血が通わなかったことでの症状であり、軽症であれば腸を休めながら、対症療法です。整腸剤を内服しながら、水分補給と腸を休ませることで数日で改善します。
重症の場合
重症化すると、以下の治療が必要になることがあります。
- 入院管理(腸の安静を保つため)
- 手術(腸が壊死した場合や穿孔がある場合)
腹痛がひどい場合は入院が必要となる場合があります。 通常は一時的な虚血(血の巡りが悪い)ですが、そのまま壊死するほど虚血になることも稀にありその場合は手術が必要となります。ただ、かなり稀です。
虚血性大腸炎の予防方法
虚血性大腸炎を起こしたことがある方は、再発をすることもしばしばあります。それを防ぐために予防が大切です。
①便秘を防ぐ
まずは便秘を防いでおくことが大切です。便秘になると腸管圧が上がることが多くなるため、再発のリスクがあります。再発予防にも便秘のコントロールは大切です。
- 食物繊維を多く含む食事(野菜・果物・全粒穀物)を摂取
- 十分な水分補給を心がける
- 適度な運動を習慣化する
② 血流を改善する
- 動脈硬化を防ぐ(塩分・脂肪の多い食事を控える)
- 血圧や血糖値を適切に管理する
- 禁煙・節酒を心がける
生活習慣病の改善は意味があります。特に動脈硬化はさまざまな病気の原因となるため、虚血性腸炎の予防だけにとどまらずしっかりと治療をすることが大切です。
③ 過度な腹圧を避ける
便秘時に無理にいきまないなど、便秘の時に強くいきむと発症しやすく、便の出が悪いときには緩下剤を使うことも検討しましょう。
まとめ
虚血性腸炎は、多くの場合軽症で自然に回復しますが、重症化すると手術が必要になることもあります。腹痛や血便の症状がみられたら、早めに医療機関を受診し、適切な治療を受けることが大切です。
血便を伴う腹痛がある場合には消化器内科を代表する内科への受診をおすすめします。