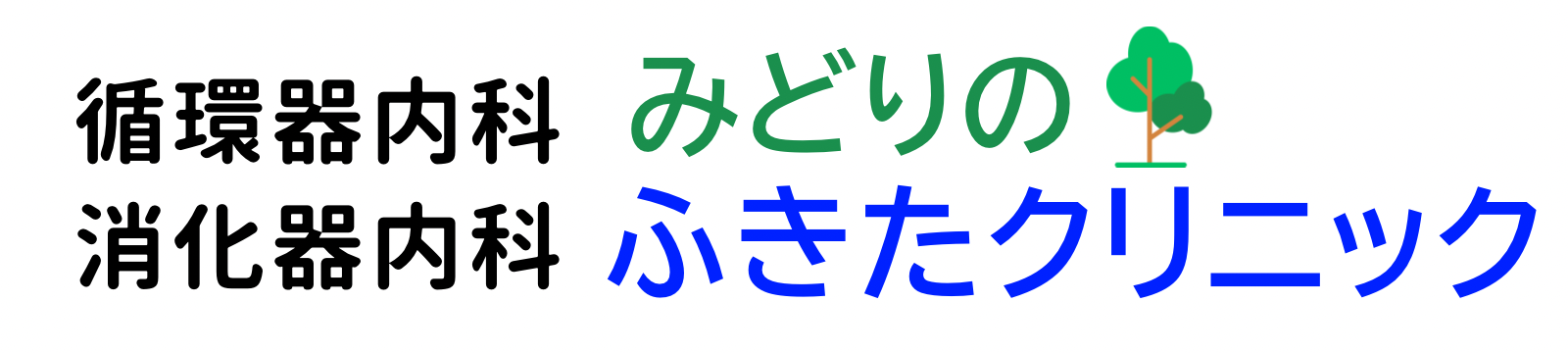はじめに
私たちの体には、本来害のないものに対しても「異物」として反応してしまうことがあります。それがアレルギー反応です。その中でも命にかかわるほど強い反応を起こすことがあり、それを「アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)」と呼びます。
アナフィラキシーは突然起こり、急速に進行するため、正しい知識と迅速な対応が命を救います。この記事では、アナフィラキシーの原因、症状、対応方法、予防策について丁寧に解説します。
アナフィラキシーとは何か?
アナフィラキシーとは、アレルギーによって起こる急激で全身的な反応です。アレルギーには花粉症のような軽いものから、重症なものまであり、これは最も重いタイプです。
アレルギー反応の最も重いタイプ
アナフィラキシーの多くの場合、アレルゲン(アレルギーを引き起こす物質)が体に入ってから数分〜30分以内に症状が出ます。
この病気は場合によっては、血圧が急激に下がったり、呼吸困難や意識障害を引き起こしたりして、命の危険につながることもあります。
そのため疑ったらすぐに対処が必要です。
アナフィラキシーの原因
アナフィラキシーを引き起こす、主なアレルゲン(アレルギーの原因物質)は以下のようなものがあります。
食べ物
- ピーナッツ、クルミなどのナッツ類
- 卵、牛乳、小麦、エビ、カニ、魚類 など
アレルギーを起こしやすい食品はきまっており、ナッツ系、卵系、甲殻類などです。これらで以前に症状が軽くでも出たことがある方は一度検査をしておくことをお勧めします。
薬剤
- 抗生物質(ペニシリンなど)
- 解熱鎮痛薬(アスピリンなど)
- ワクチン
- 造影剤(CTやMRIで使われる)など
薬剤もアナフィラキシーの原因となります。ワクチン接種後に病院に15分いるように言われる理由もアナフィラキシーの危険性があるからです。
また、抗菌薬、造影剤などは引き起こすことがある薬として知られていますが、どんな薬剤でも人によっては大なり小なりアレルギーのリスクは愛肺転移ます。
昆虫の毒
- ハチ(特にスズメバチやアシナガバチ)に刺されること
昆虫に刺されてアナフィラキシーは有名だと思います。これも原因となります。
運動やその他の要因
- 特定の食べ物を食べた後の運動(食物依存性運動誘発アナフィラキシー)
- ラテックス(ゴム製品)などに触れること
これらさまざまな原因で起こり得ますが、多くは蜂や、薬品、食事由来である場合が多いです。
アナフィラキシーの症状
アナフィラキシーの症状は、全身にわたってさまざまに現れます。そしてかならずおこるのが皮膚症状です。
皮膚の症状
- じんましん(かゆみをともなう赤い発疹)
- 顔やまぶた、唇の腫れ
アレルギー反応では皮膚の症状が出ます。具体的には皮膚が赤くなる(皮疹)だったり、粘膜が腫れるなどの症状です。
呼吸器の症状
- 息苦しさ、せき、ぜんそくのような呼吸音
- 声がれ、のどのつかえ感
呼吸器の症状は気道などの空気の通り道の粘膜が腫れることで起こります。これらは比較的注意が必要な症状です。
消化器の症状
- 腹痛、吐き気、嘔吐、下痢
腸の粘膜が腫れることでお腹の症状も起こりえます。
循環器の症状
- めまい、意識がぼんやりする
- 血圧の低下、意識消失
すべての症状が同時に出るとは限らず、症状の出方は人によって違います。アナフィラキシーを疑う場合にはかならず皮疹と、消化器、呼吸、循環器の症状が一つまたは複数でてきます。
アナフィラキシーが疑われたときの対応
基本的にはアナフィラキシーは命に関わる病気のため様子はみれません。うたがったらすぐに病院へ受診する必要があります。
すぐに救急車を呼ぶ(119番)または病院へ行く
少しでも「おかしい」「アナフィラキシーかもしれない」と思ったら、ためらわずに119番通報しましょう。待っているうちに症状が悪化することがあります。
特に動けないほどひどいなどの場合は様子みてはいけません。
エピペンの使用(処方されている方)
すでに過去にアナフィラキシーの既往がある方には、自己注射薬「エピペン®」が処方されていることがあります。もし処方されていて注射について指導を受けている場合は指示通りに注射し、その後病院へ受診するようにしてください。
体を仰向けにして足を高くする
もし、意識がある場合は、救急車などを待つ際には仰向けに寝かせ、足を少し高くします(ショック体位)。呼吸が苦しい場合は、座ったままの方が楽なこともあります。
アナフィラキシーを防ぐために
原因を知り、避けることが最も重要
一度アナフィラキシーを起こした方は、原因となったアレルゲンを正確に特定し、徹底して避けることが大切です。
- 食品ラベルのチェック
- 外食時の事前確認
- ハチの巣のある場所を避ける
- 医療機関での事前申告(薬剤アレルギー)
などです。しっかりと対策を行いましょう。
家族や周囲の人とも情報を共有する
本人が対応できない場合に備えて、エピペンの使い方やアレルギー歴を家族・職場・学校などに伝えておくことが大切です。
アナフィラキシーは「正しく恐れる」ことが大切
アナフィラキシーは怖いものです。しかし、正しい知識と準備があれば、命を守ることができます。必要以上に怖がる必要はありません。
心配な症状がある方は、早めにご相談ください。また、医療機関ではアレルギー情報はかならず共有するようにしてください。
参考文献・根拠となる情報
- Simons FE, Ardusso LR, Bilo MB, et al. World Allergy Organization anaphylaxis guidelines: 2013 update of the evidence base. Int Arch Allergy Immunol. 2013;162(3):193–204. DOI: 10.1159/000354543
- 日本アレルギー学会 アナフィラキシーガイドライン2022年版
- Lieberman P, et al. Anaphylaxis–a practice parameter update 2015. Ann Allergy Asthma Immunol. 2015;115(5):341–384. DOI: 10.1016/j.anai.2015.07.019