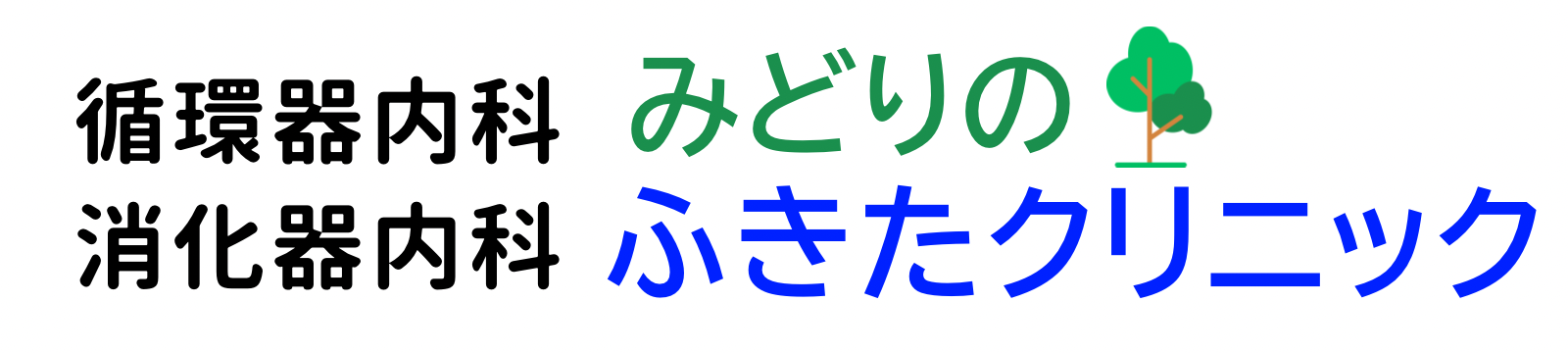はじめに
インフルエンザワクチンは毎年打っている。そういう方も多いかもしれません。しかし、インフエンザワクチンを打ったのに、インフルエンザになった….そんな印象もあるかもしれません。
実際にインフルエンザワクチンは打てばインフルエンザに全く罹らなくなるというワクチンではありません。
しかし、インフルエンザワクチンは接種することで発症をある程度減らし(目安30〜60%程度)、とくに重症化(入院・死亡など)を減らすなど接種による有効性は多くの研究で示されています。
そのため、特に重症化のリスクが高い基礎疾患がある方や65歳以上では接種がすすめられています。
今回はそんなインフルエンザワクチンは接種すると実際にどのような効果がいつからでるのか?などについて解説します。
インフルエンザワクチンを打つことでどれくらい「発症」を防げるの?
同じ条件の人を「接種しない100人」と「接種した100人」で比べると、接種したグループではおおむね30〜60人分の発症が防げる、そんなイメージとなります(年やウイルスの型によって上下します)。
ワクチンを打てばかならずしも発病を防ぐわけではありません。インフルエンザワクチンの最も大きな効果は、「重症化」を予防することです。
国内の研究では、65歳以上の高齢者福祉施設に入所している高齢者でインフルエンザワクチンを接種することで34~55%の発病を阻止し、82%の死亡を阻止する効果があったとされています。
インフルエンザワクチンを打つことでどれくらい「重症化」を減らせるの?
インフルエンザワクチンの1番の目的はこの重症化予防です。重症化は入院や死亡などインフルエンザを契機に重症な症状を起こす場合です。
入院・死亡のリスクを下げる
高齢の方や基礎疾患のある方で、入院や死亡のリスクを下げることが多くの研究で示されています。
心臓・血管の合併症も減らせることがある
心臓病(心筋梗塞など)の既往がある方では、ワクチン接種で主要な心血管イベントが減るという質の高い研究が複数あります。心臓に持病のある方では“インフルエンザ対策”が心臓を守ることにもつながります。
赤ちゃんも守れる妊婦さんの接種
妊娠中の接種はお母さんの重症化を減らし、生後6か月未満の赤ちゃんの発症・入院も減らすことが示されています。
また、子どもの接種は、家庭・地域全体の発症率を下げる“波及効果”が期待できます。
インフルエンザワクチンは効果が出るまでと、どれくらい続く?
インフルエンザワクチンの効果はどれくらいででて、どれくらい続くとされているのでしょうか。
接種後に効果が出てくるタイミングは?
接種後およそ2週間で免疫が立ち上がります。日本では効果の実感はおよそ5か月を目安に案内されます。そのため、流行の始まる前(例年12月頃)に間に合うよう、10〜11月の接種が理想的です。
効果が年によって差が出る理由は?
流行するウイルスとワクチン株の「ずれ(ミスマッチ)」などにより、年による効果が差が出ます。(いわゆる当たり年かどうか)
インフルエンザワクチンの安全性と副反応は?
では、インフルエンザワクチンの安全性や副反応はどうでしょうか?
よくある副反応(1〜3日程度で自然に軽快)
注射部位の痛み・赤み、微熱、だるさ、筋肉痛など。つらい場合は解熱鎮痛薬で対応できます。強い・長引く場合はご相談ください。
まれに起こりうる重い副反応
アナフィラキシー(重いアレルギー)
頻度は約100万回に1〜2回と非常にまれです。アナフィラキシーはインフルエンザワクチンに限らず全てのワクチンでリスクがあり、また薬剤や食事でも起こる可能性はあります。接種する医療機関では、もしもの際に備えており、接種後体調をみてから帰宅してもらっています。
ギラン・バレー症候群(GBS)
ごくわずかなリスク増が示された研究がありますが、絶対数は非常に小さい(100万人あたり1〜2人程度のオーダー)とされています。一方で、インフルエンザ自体もGBSのリスクを上げる可能性があるため、総合的には接種の利益が上回ると判断されています。
卵アレルギーの方へ
インフルエンザワクチンは卵で製造されていました。そのため、ワクチンに残留する卵タンパク質は、卵アレルギーのあるワクチン接種者にリスクをもたらすと考えられていました。しかし、最近の多くの研究で、卵アレルギーのある接種者が卵アレルギーのない接種者と比べてこのような反応を起こす可能性は高くないことが実証されています。
重症の卵アレルギーがあっても多くの方で通常どおり接種可能となっています。ただ、心配な方は診察で個別に判断します。
また、もし万が一、ワクチンを適正に使用したにもかかわらず発生した副反応により健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)による医薬品副作用被害救済制度または生物由来製品感染等被害救済制度の対象となります。
インフルエンザワクチンのメリットとデメリットは?
インフルエンザワクチンを接種するかはメリットとデメリットから判断してもらうことがお勧めです。
メリット
- 発症が減る → 学校・仕事の欠席を減らし、生活の質を守りやすくなります。
- 重症化・入院・死亡のリスク低下 → 高齢者や基礎疾患のある方で特に重要。
- 心血管合併症の抑制 → 心臓病の既往がある方では追加の守りになります。
- 家族や周囲を守る → 小さなお子さんや高齢の家族、職場や学校にもよい影響
特に発症を完全ではないですが、抑えることができること。重症化のリスクが下げることができるため基礎疾患がある方や高齢の方では特にメリットが大きいです。
デメリットや制限
- 年によって効き方に差がある(流行株の違い、ミスマッチ)
- 効果は時間とともに少しずつ低下するので、毎年シーズン前の接種が基本となる
- 注射部位の痛みや微熱などの軽い副反応が出ることがある。重い副反応は非常にまれ
デメリットは副反応と、費用がおもになります。接種自体は成人であれば一回ですむため、おおきな負担にはなりません。
いつ・どのような人が受けた方がよい?
接種時期・回数については効果が出てくるまで2週間ほどかかるため、流行前の10〜11月に接種しておくのが目安となります。また、接種回数:13歳未満は原則2回、13歳以上は通常1回です。
特に接種が望ましいと考えられる患者さんは
- 65歳以上
- 心臓病、呼吸器病、糖尿病、腎・肝疾患など基礎疾患のある方
- 妊娠中の方
- 医療・介護・教育など人と接する機会の多い方、家族に乳幼児や高齢者がいる方
特にインフルエンザワクチンが有効と考えられる患者さんは上記の通りです。
まとめ
静岡市周辺で接種時期や可否に迷う方、持病やお薬が気になる方は、みどりのふきたクリニック外来でお気軽にご相談ください。状況に合わせて最適なタイミングとリスク管理をご一緒に考えます。
接種希望の方は下記を確認いただきご連絡いただければと思います。