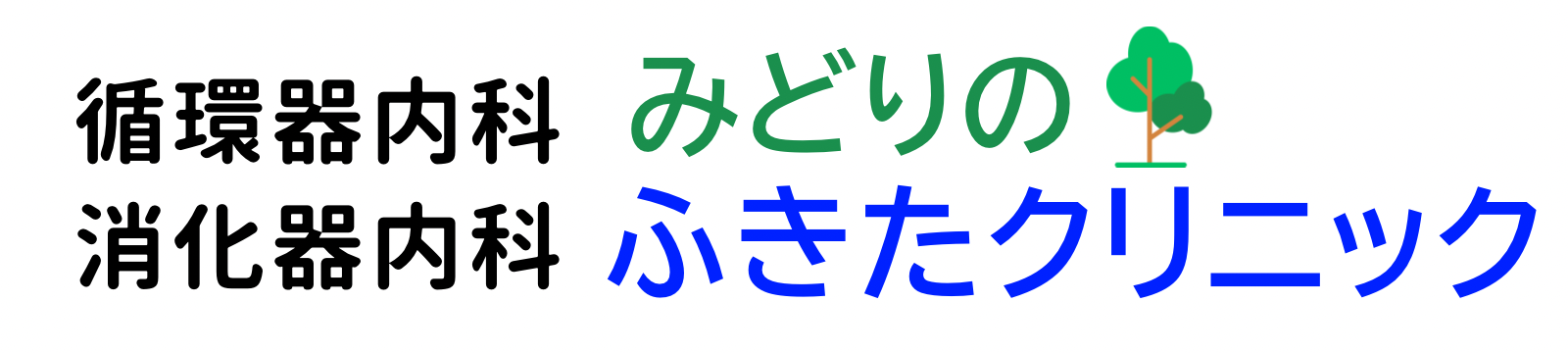無症候性高尿酸血症とは、血清尿酸値が持続的に7.0mg/dLを超えるものの痛風発作など症状がない状態を指します。症状がない場合でも、尿酸値が高い状態が続けば、将来的に痛風発作(関節炎)や尿路結石、腎機能低下などを招くリスクがあるとされます。
また高尿酸血症は高血圧・糖尿病・慢性腎臓病(CKD)など生活習慣病ともしばしば合併し、心血管疾患リスクに関連することが指摘されています。そのため 生活習慣の改善 は症状の有無に関わらず高尿酸血症管理の基本であり、「高尿酸血症の治療では肥満・高血圧・糖脂質代謝異常などに関係する生活習慣の改善が最も大切である」とガイドラインでも強調されています。
しかし、痛風発作を繰り返した方への高尿酸血症への治療の必要性はあきらかではあるものの、無症候性高尿酸血症の治療、特に薬物治療については議論があります。今回は無症候性高尿酸血症の治療についてまとめます。
治療介入の必要性(生活習慣改善・薬物療法)
無症候性高尿酸血症の治療についてはまずは 食事療法や減量指導(プリン体摂取制限、アルコール摂取の節制、高果糖飲料の制限、適正体重の維持など)が推奨されます。実際、無症候性高尿酸血症患者には積極的に食事指導を行っている医師も多くいます。
一方で、無症候性高尿酸血症に対する 薬物療法の必要性 については慎重な判断が求められます。
欧米のガイドラインでは「症状のない高尿酸血症への尿酸降下薬投与は推奨しない」とされており、痛風発作を繰り返すようになって初めて治療介入するのが基本です。これは、高尿酸血症に対する介入が腎障害や心血管疾患の発症予防につながるか明確なエビデンスが十分でないためです。
しかし日本のガイドラインでは、生活習慣修正を行った上で一定の基準を満たす場合には薬物療法を検討する方針が示されています。症状がなくとも尿酸値が非常に高い症例では将来的な痛風発症リスクが無視できず、実際尿酸9mg/dL以上では年間約5%が痛風発作を起こすとの報告もあります。このため日本では、将来の重症痛風(痛風結節の形成など)を予防する観点から、無症候性高尿酸血症の段階で早めに治療介入することも「選択肢」として認められています。
ただし、薬物療法を開始するかどうかは尿酸値の高さや合併症の有無を総合的に見て判断され、漫然と全例に行うべきではありません。まずは生活習慣改善のみで経過を観察し、必要と判断される場合に薬物療法を追加するのが一般的です。
治療介入を開始する基準と目標尿酸値
日本の『高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン(第3版)』では、無症候性高尿酸血症に対する薬物治療開始の目安が明確に示されています。そのポイントは以下のとおりです。
開始基準(尿酸値と合併症の有無)
合併症のない場合は血清尿酸値が9.0mg/dL以上で薬物療法(尿酸降下薬)の導入を考慮します。
一方、腎障害(CKDや尿路結石)、高血圧、糖尿病、脂質異常症・メタボリックシンドローム、虚血性心疾患などの合併症がある場合は、やや厳しめに8.0mg/dL以上を目安に薬物療法を検討します。これら「合併病態」のある症例では、高尿酸血症がこれら疾患をさらに悪化させる可能性があるため早期介入を考慮します。
逆に言えば、合併症がなく尿酸値がそれほど高くない(例えば7~8mg/dL台)場合は、直ちに薬物治療を開始せず生活指導で経過を見ることが推奨されます。実際、米国ガイドラインとの比較でも、日本では「合併症なしなら9.0以上、あれば8.0以上で薬物治療を考慮し、目標は6.0以下」と明記されていますが、米国では無症候性高尿酸血症に尿酸降下薬は用いない方針です。
目標尿酸値は?
一度薬物治療を開始した場合の降下目標は、血清尿酸値6.0mg/dL以下にコントロールすることです。
尿酸の生体内での溶解限界が約6.4mg/dLとされ、それ以下に保つことで尿酸塩結晶の沈着予防や既存結晶の溶解が期待できます。したがって痛風発作予防のため、痛風患者のみならず無症候性高尿酸血症の治療においても尿酸値6mg/dL以下を目指すことが望ましいとされています。
(補足: なお痛風結節を有するような重症痛風患者では目標5mg/dL以下とすることも推奨されていますが、無症候性高尿酸血症の段階では通常6mg/dL以下が目標となります。)
合併症への対応
上記のような合併症を有する患者では、まず合併症自体の治療を優先し、その上で尿酸も下げていく方針が推奨されます。
具体的には、高血圧を合併する場合は尿酸低下の効果が証明されているロサルタン(尿酸排泄促進作用を持つARB)を用いる。
脂質異常症(高トリグリセリド血症)にはフェノフィブラート、糖尿病にはSGLT2阻害薬やピオグリタゾンなど、それぞれ尿酸値を下げる作用を併せ持つ治療薬を選択すると一石二鳥であると報告されています。
このように合併症治療と尿酸管理を両立できる薬剤の活用も選択肢となります。また、腎障害(CKD)を合併する高尿酸血症については、日本のガイドラインは「腎保護目的での尿酸降下薬使用」を世界に先駆けて推奨しています。
高尿酸血症が慢性腎臓病の進行因子となり得るため、腎機能低下例では症状がなくても尿酸降下薬の積極的導入が考慮されます。一方、高血圧や心不全を合併する高尿酸血症では、尿酸降下薬投与による心血管イベント予後改善効果は現時点でエビデンス不足のため積極的には推奨されません。
(※合併症としての高血圧や心不全そのものの治療は必要ですが、尿酸値管理はあくまで痛風・腎障害予防の観点で判断する)。
尿酸の治療導入時の注意
無症候性高尿酸血症に対し薬物療法を開始する際は、患者の状態に応じて慎重に適応を判断する必要があります。
ガイドラインでも「薬物治療導入は8.0mg/dL以上を目安とするが適応は慎重にすべきで、現時点でのエビデンスや薬物副作用について十分情報提供し、患者の納得のうえで開始すること」が望ましいと記載されています。
つまり、治療のメリット・デメリットを説明し、患者の希望も踏まえて共同意思決定することが大切です。
また、尿酸降下薬には重篤な副作用(スティーブンス・ジョンソン症候群や薬剤性過敏症症候群〈いわゆるアレルギー性の重症薬疹〉、劇症肝炎など)が報告されたものもあり、開始後は副作用に十分注意する必要があります。
このような理由から、症状のない段階での薬物治療開始は「治療しないリスク」と「治療するリスク」を天秤にかけて慎重に決定されます。患者さん自身も医師とよく相談し、尿酸値や合併症の状態を見ながら治療方針を決めていくことが重要です。
治療中の検査・フォローアップ方法
無症候性高尿酸血症と診断された患者の経過フォローでは、定期的な血液検査による尿酸値モニタリングが欠かせません。フォローアップの具体的な方法は、治療介入の内容(生活習慣改善のみか薬物療法ありか)や合併症の有無によって多少異なります。
生活習慣改善のみで経過を見る場合
食事指導や減量など生活習慣の修正を開始したら、約3か月後にまず尿酸値の変化を確認します。この時点で尿酸値が7.0mg/dL未満まで低下していれば、生活習慣改善の効果があったと判断し、そのまま継続します。
以降のフォローは3~6か月に1回程度、定期的に尿酸値を測定します。生活習慣の改善効果が不十分で尿酸値が依然7mg/dL以上と高い場合や、基準値(前述の8~9mg/dL)を大きく超える状態が続く場合には、適宜薬物療法の導入を検討します。その判断も含め、定期健診や外来受診の際に尿酸値をチェックしながら経過観察することが大切です。
薬物療法を行う場合
尿酸降下薬を開始したら、開始後約2週間で一度安全性チェックの血液検査を行います。これは薬剤による副作用の早期発見や、腎機能・肝機能への影響を確認する目的です。
特に腎機能が低下している患者では薬剤の用量調節が必要な場合があるため、初期には腎機能検査を含めたフォローが重要です。その後、尿酸降下薬の効果判定として投与開始約4週間(1か月)で尿酸値を再検査します。
一般に尿酸降下薬による尿酸低下作用は投与開始後約4週で定常状態(プラトー)に達するとされるため、1か月時点の値を目安に薬剤効果を評価します。目標達成に至っていなければ、以後1か月ごとに尿酸値を測定しながら薬剤容量の漸増調整を行います。急激に尿酸を下げると痛風発作を誘発しやすいため、月に0.5~1.0mg/dL程度ずつ段階的に尿酸値を下げていくペースで投与量を調整し、最終的に6.0mg/dL以下を目指します。
フォロー頻度と検査項目
治療開始~6か月間は、上述のようにおおむね毎月1回の頻度で血液検査を行い、尿酸値が目標に達するまで経過を追います。副作用監視の意味でも、治療初期は月1回程度の密なフォローが推奨されます。
6か月以降で尿酸値が安定し症状も問題ないようであれば、フォロー間隔を少し延ばすことも可能です。
合併症が特にない場合は2~4か月に1回程度の血液検査で尿酸値を確認し、合併症がある場合はその合併症の経過観察時(例えば糖尿病や腎臓病で定期的に採血するタイミング)にあわせて尿酸値も測定する、といった形でフォローします。定期検査の項目としては、最低限血清尿酸値、腎機能(血清クレアチニン値やeGFR)、肝機能(AST/ALTなど)を確認します。
特にフェブキソスタットなど一部の尿酸生成抑制薬は肝機能障害のリスクが報告されているため、初期6か月間は定期的に肝機能検査を行うことが推奨されています。
尿酸排泄促進薬を使用している場合は、尿路結石予防のため十分な水分摂取や尿アルカリ化を指導するとともに、必要に応じて尿検査で尿中尿酸結晶の有無を確認することも考慮します。
(※尿検査頻度に明確な規定はありませんが、副作用予防の観点から注意が必要です)
長期的なフォロー内容
症状のない患者でも、フォローアップでは痛風発作など新たな症状の出現にも注意します。万一、治療中に関節痛や腫れなど痛風発作が疑われる症状が出現した場合は、速やかに主治医に相談し対処します。
また尿酸降下薬の内服継続中は、副作用症状(皮疹、倦怠感、食欲不振など肝障害兆候)の有無についても毎回問診し、異常があれば早めに検査を行います。加えて、生活習慣の改善は引き続き重要な課題です。高尿酸血症の背景にある肥満・高血圧・耐糖能異常・脂質異常などの管理も並行して行い、必要に応じて専門医と連携しながら患者全体のリスク低減を図ります。
特に体重や食習慣は時間の経過とともに元に戻りやすいため、定期フォロー時にリバウンドがないか指導・確認していくことが大切です。
まとめ
以上のように、日本における無症候性高尿酸血症の管理は「生活指導の徹底」を土台としつつ、尿酸値や合併症の状況に応じて適切な時期に薬物療法を開始し、開始後は目標値達成まで継続的にモニタリングするという方針に基づいています。
この方針に従って患者さん個々の状況に合わせた介入とフォローアップを行うことで、将来的な痛風発作や合併症発症の予防につなげていきます。適切な管理の継続により、症状のない高尿酸血症患者においても健康リスクを最小限に抑えることが可能です。各種ガイドラインやエビデンスを踏まえ、患者と医療者が二人三脚で長期管理に取り組むことが重要と言えるでしょう。
参考文献: 日本痛風・核酸代謝学会ガイドライン改訂委員会編『高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン 第3版(2019年改訂・2022年追補版)』ほか、日本内科学会雑誌・Circulation Journal掲載のガイドライン解説記事、専門医による解説サイトなど。