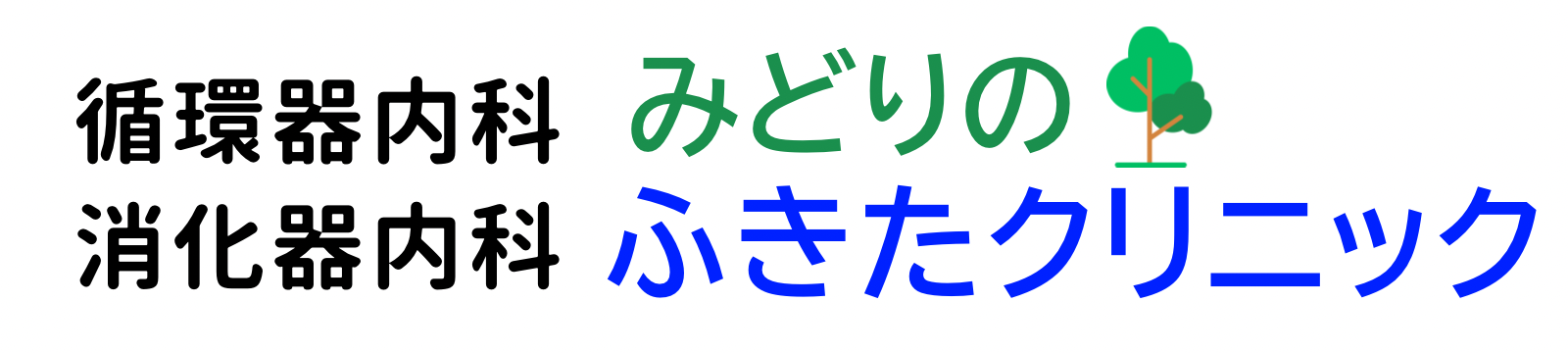はじめに
ある日突然、
「息が苦しくて、胸が痛い」
「少し歩いただけで息があがる」
こうした症状が現れたとき、肺の血管に血のかたまりが詰まる「肺塞栓症(はいそくせんしょう)」が起きている可能性があります。
この病気は、早期発見と治療が命を左右することがある一方で、前ぶれが少ないこともあります。この記事では、肺塞栓症の原因・症状・診断・治療について、わかりやすく解説します。
肺塞栓症とは?
肺塞栓症は、血のかたまり(血栓)が肺の動脈に詰まってしまう病気です。
血栓は多くの場合、脚の静脈(深部静脈血栓症:DVT)でできたものが血流に乗って肺まで運ばれ、肺動脈を塞いでしまうことで発症します。このため、肺塞栓症はDVTとまとめて「静脈血栓塞栓症(VTE)」と呼ばれることもあります。
肺塞栓症の主な症状
肺塞栓症の症状には下記のようなものがあります。
- 突然の息切れ、呼吸困難
- 胸の痛み(特に深呼吸や咳で悪化)
- 動悸
- 失神、めまい
- 発熱
- 咳、血の混じった痰
特に胸の痛みや呼吸苦がメインの症状です。肺塞栓症は命に関わる病気であり重症の場合、心停止やショック状態で救急搬送されることもあります。ただし、軽症では息切れだけで発見が遅れるケースもあるため注意が必要です。
肺塞栓症の原因・リスク因子
肺塞栓症の多くは、深部静脈血栓症(DVT)で足にできた血栓が肺に飛んでいくことよって起こります。そのため、DVTを予防することがまずは大切です。リスクとしては
- 手術後(特に整形外科やがん手術)
- 長時間の安静(入院、骨折など)
- 長距離の移動(エコノミークラス症候群)
- 妊娠・出産直後
- がんの治療中
- 高齢
- ピル(経口避妊薬)の使用
- 先天的な血液凝固異常
などがあり、これらがある方は注意が必要です。
肺塞栓症の診断方法は?
肺塞栓の診断方法について解説します。
問診・バイタルの評価
まずは問診と血圧などのバイタルサインのチェック、診察が大切です。
- 呼吸数や酸素飽和度(SpO₂)をチェック
- Wellsスコア、Genevaスコアなどの臨床予測ルールを使う。
血液検査(Dダイマー)
採血検査も重要な検査となります。特に疑わしい場合はD-dimerをとることで評価が可能です。
- 高値ならば肺塞栓症の可能性あり
- ただし、心筋梗塞や感染症でも上昇するため過信は禁物
画像検査
また、最終的な診断は画像検査で行います。特に造影CTで直接肺動脈を確認することで診断します。
- 造影CT(CTPA):肺動脈の血栓を直接確認できる標準検査
- 心エコー:重症例では右心負荷(肺高血圧)の評価に有用
- 下肢静脈エコー:DVTの評価のために行う。
肺塞栓症の重症度分類と治療方針は?
肺塞栓症は、重症度によって治療が大きく異なります。
日本循環器学会「VTE診療ガイドライン(2020)」に準拠すると以下のようになります。
高リスク(致死的)の患者
血圧が低い(ショック、心停止)の場合は高リスクで致死的です。この場合はクリニックであればすぐに総合病院へ救急搬送となります。また、治療も一分一秒をあらそいます。
- 全身的血栓溶解療法:組織プラスミノーゲンアクチベーター(tPA)などを使用
- カテーテル誘導血栓溶解療法:出血リスクが高い場合や全身療法が禁忌の場合に検討
- 外科的血栓除去術:他の治療が無効または禁忌の場合に考慮
※CHESTガイドラインでは、血行動態が不安定なPEに対して全身的血栓溶解療法を推奨しています(Grade 2B) 。
中リスクの患者
血圧は保たれているが、心エコーで右心負荷や心筋障害の所見がある場合が中リスクです。この場合も当然入院も考慮されます。
治療:抗凝固療法が基本、場合により溶解療法も検討されます。
低リスクの患者
生命徴候が安定、右心負荷もないなど、症状が現れていない場合です。慎重に判断をしつつ内服での治療も検討されます。
治療:DOAC(直接経口抗凝固薬)による外来管理も可能
抗凝固療法(血を固まりにくくする薬)
第一選択:DOAC(アピキサバン、リバーロキサバンなど)
- 初期から使用可能
- ワルファリンと比べて出血リスクが低く、モニタリング不要
- 他の選択肢:ヘパリン+ワルファリン(妊婦・腎機能低下など特殊例で使用)
治療期間は、3〜6か月が標準ですが、再発リスクによっては長期投与が必要なこともあります。
特殊な患者群における治療について
癌患者では低分子量ヘパリン(LMWH)が第一選択とされてきましたが、最近の研究ではDOACsも安全かつ有効であることが示されています 。
妊婦ではワルファリンやDOACsは胎児への影響が懸念されるため、LMWHが推奨されます。
肺塞栓症の予防はできるの?
肺塞栓症は予防が最も重要です。まずは深部静脈血栓(DVT)を作らないことが大切です。
また、以下は、2020年ガイドラインで推奨される予防法です。
- 術後早期の歩行
- 弾性ストッキング、空気圧ポンプ(IPC)の活用
- リスクが高い患者では、予防的な抗凝固療法(例:低用量DOAC)
- 飛行機や長距離移動では、1時間に1回足を動かす、水分をとる
これらはDVTを作らないようにする注意点です。肺塞栓症はなると命に関わることがある病気であり、しっかりと対策をすることが望まれます。
おわりに
肺塞栓症は突然発症し、命に関わることもある病気ですが、多くは予防と早期治療で重症化を防ぐことができます。息切れや胸の違和感があるとき、「ただの疲れ」と思わずに、まずは医療機関を受診してみてください。
みどりのふきたクリニックでは、DVT・PEに関する評価や、予防・治療の相談も受け付けています。ご自身やご家族の健康を守る第一歩として、どうぞお気軽にご相談ください。