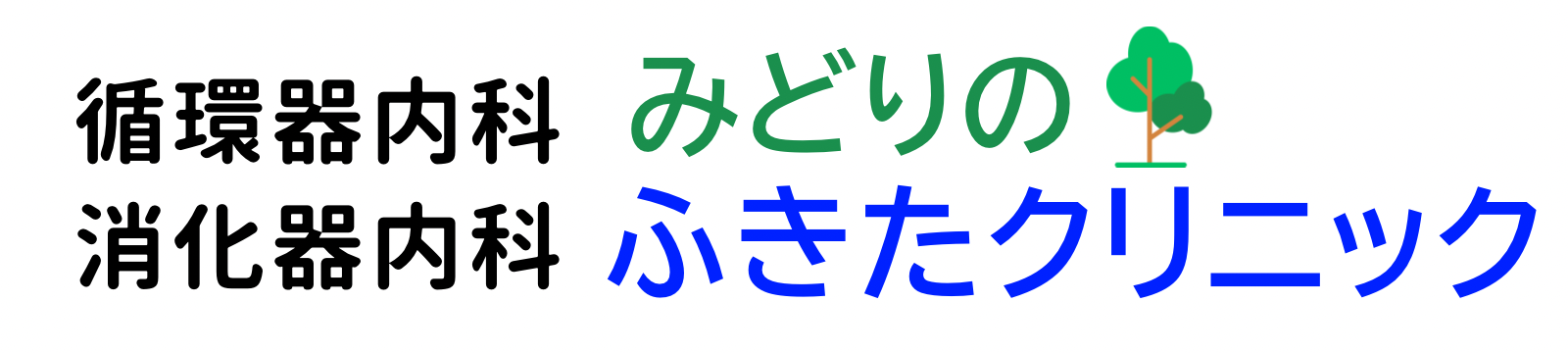狭心症とは?
狭心症とは、心臓にある冠動脈という血管が狭くなり、心臓に十分な血液が供給されなくなることで、胸の痛みや圧迫感を感じる病気です。
心臓の筋肉(心筋)は、血液によって酸素や栄養を受け取りますが、冠動脈(心臓の血管)が狭くなったり詰まったりすると、血流が滞り、胸の不快感を引き起こします。狭心症は心筋梗塞の一歩手前の状態であると考えられます。
狭心症の種類は?
狭心症は主に原因や状態によって以下の3種類に分類されます。
労作性狭心症
運動や労作の際に発症する狭心症(走る、階段の上り下りをする)です。労作性狭心症では動脈硬化によって冠動脈が狭くなっているため、心臓の負担が増えるような動作を行うと、酸素が不足し、胸の痛みが現れます。
自転車に乗る、階段を登るなどほぼ同じ程度の運動やストレスで症状を生じます。労作性狭心症では、安静にすることで比較的速やかに症状が改善するはずです。ニトロを持っている場合はすぐに内服します。
不安定狭心症
安静な状態でも胸痛が起こる狭心症です。労作性狭心症よりもさらに進行した状態で、危険度が高いです。不安定狭心症は名前の通り冠動脈が狭くなることが進行して病状が不安定であり、いつ心筋梗塞へ進行してもおかしくない状態です。
3.冠攣縮性狭心症
安静時や睡眠中に突然発症する狭心症です。夜間などに冠動脈が一時的に強く収縮することで血流が遮断され、発作が起こります。ストレスや寒冷、喫煙などが引き金になることがあります。カテーテルの検査で詰まりを確認しても詰まりが見つからず、特殊な薬剤を投与することで診断できることが特徴です。
狭心症の症状は?
狭心症の症状は下記のような症状です。
- 胸の圧迫感や締め付け感(数分間持続することが多い)
- 左肩や腕、あごに放散する痛み
- 息苦しさや冷や汗
- 胃の不快感や吐き気(特に高齢者に多い)
狭心症の症状は多くは数分、少なくとも30分以内に改善する場合がほとんどです。
典型的には左の胸〜左肩に胸が締め付けられるような痛みが数分あり、冷や汗を伴います。これらの症状が現れた場合は狭心症を考える必要があります。
狭心症の原因とリスク要因
狭心症の発症には、以下のような要因やリスクが関係しています。
- 動脈硬化(高血圧、高コレステロール、糖尿病による血管の老化)
- 喫煙(血管を収縮させる作用がある)
- 肥満や運動不足(血流の悪化を招く)
- ストレス(血管の収縮を引き起こすことがある)
- 過度のアルコール摂取(血圧上昇の原因になる)
- 家族歴(遺伝的要因も関与する)
狭心症は肥満、動脈硬化、喫煙、家族歴などさまざまなリスクがあります。
特に生活習慣病などにより動脈硬化が進行すると狭心症を発症しやすくなります。生活習慣病の方がしっかりと治療を行なっておいた方が良い理由の一つです。
また、家族の方で狭心症や心筋梗塞のある方はリスクが高いことも知られています。
狭心症の診断
狭心症の診断は症状だけではできず、さまざまな検査や診察で行います。具体的には、以下のような検査が行われます。
- 心電図検査:心臓の電気的な活動を記録し、異常を検出
- 運動負荷試験:運動時の心電図の変化を確認
- 心臓超音波(エコー)検査:心臓の動きや血流を評価
- 冠動脈CT検査:冠動脈の狭窄の有無を調べる
- 心臓カテーテル検査:血管内の状態を詳細に確認し、治療の判断を行う
狭心症は一時的な心臓の虚血状態なため、心電図や心エコーでは発見できないケースもあります。そのため症状等から疑わしい症状があれば、心臓MRIやシンチなどの画像検査や、運動負荷にて診断を行います。
また、ホルター心電図によって、発作が起きている時の心電図を記録するという方法もありますが、診断的治療で、治療薬のニトロを発作があるときに使う方法もあります。
ここの患者さんごとに判断します。
狭心症の治療と管理は?
狭心症の治療には、生活習慣の改善と薬物療法、必要に応じてカテーテルや手術が選択されます。
生活習慣の改善
まず狭心症は動脈硬化により引き起こされている場合が多いです。そのため、症状がまだない方の予防・管理するためには、日々の生活習慣の見直しが重要です。
- 禁煙(喫煙は血管を収縮させ、リスクを高める)
- 適度な運動(ウォーキングや軽い筋トレを継続)
- バランスの取れた食事(塩分や脂質を控え、野菜や魚を多く摂る)
- ストレス管理(リラックスする時間を確保)
- 適正体重の維持(肥満は動脈硬化の原因になる)
これは狭心症がひどくなる前の予防として重要であり、生活習慣病の治療と内容は類似しており、つまり糖尿病、高血圧、高脂血症の治療の重要性です。
薬物療法
一度症状が発症し頻回である場合は、症状を抑え、心臓の負担を軽減するために、以下のような薬が処方を検討します。
- 硝酸薬(ニトログリセリン):血管を広げ、症状を緩和する作用があります
- カルシウム拮抗薬:血管の収縮を防ぎます。特に冠攣縮性狭心症ではよく聞きます
- 抗血小板薬(アスピリンなど):血栓を防ぎ、血流を改善します。カテーテル治療後の再狭窄予防にも重要です
- スタチン系薬:コレステロールを下げ、動脈硬化を予防です
また、狭心症発作を疑う場合には、ニトログリセリンの舌下錠を発作時に使用する場合があります。ニトログリセリンは発作時の症状を改善させるほか、効果の確認で診断的な治療を行うこともできます。
血管治療(カテーテル治療・バイパス手術)
薬では十分な効果が得られない場合や冠動脈の狭窄の度合いがひどい場合は、冠動脈の異常を調べる検査、冠動脈の狭窄を改善する治療が行われます。
- カテーテル治療(PCI):細い管(カテーテル)を血管内に挿入し、狭くなった部分を拡げる治療
- 冠動脈バイパス手術(CABG):狭窄部を迂回する新たな血流路を作る治療
狭心症と上手に付き合うために
狭心症は、症状が起こり始めた時に早く気づき、適切な治療と管理が大切です。
- 定期的な健康診断を受ける(早期発見・早期治療が重要)
- 狭心症のような症状が頻発したらすぐに病院へ相談する
- 治療は中断せずに続ける
- 血圧やコレステロールは普段から治療をしておく
狭心症は放置すると心筋梗塞などの深刻な病気につながる可能性があります。適切な管理と予防を心がけ、健康的な生活を送りましょう。
何か気になることがあれば、当院へご気軽にご相談ください。