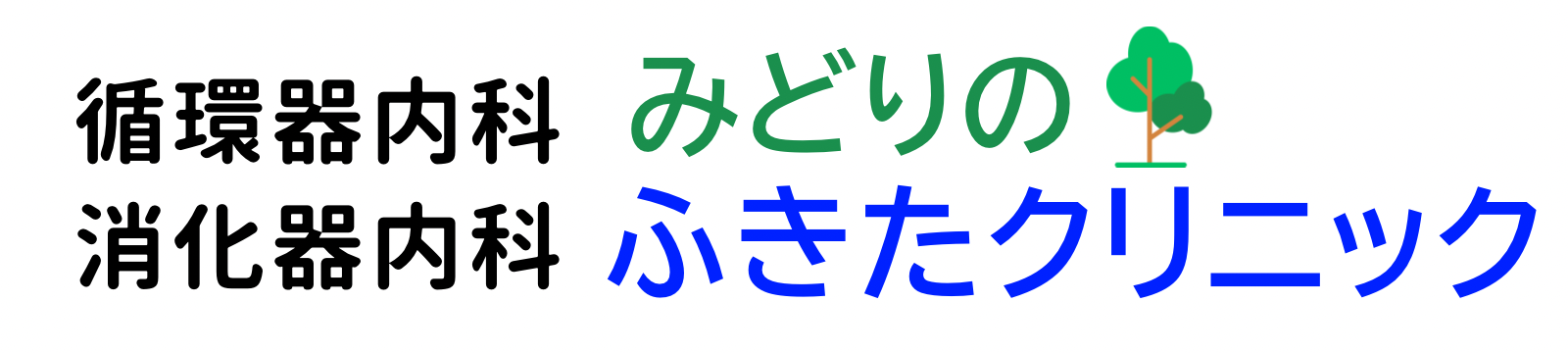弁膜症
弁膜症とは、心臓の弁が正常に機能しなくなる病気です。
心臓には4つの弁(大動脈弁・僧帽弁・三尖弁・肺動脈弁)があり、これらが扉のように空いたり閉まったりすることで血液の流れを適切にコントロールしています。
これらの弁が狭くなったり(狭窄)、閉じなくなったり(逆流)すると、心臓に負担がかかり、全身に十分な血液を送ることができなくなり、心不全など重篤な状況になってしまいます。
弁膜症の種類
心臓の弁はそれぞれが、閉じる弁と開く弁があることで、適切に血液を流していきます。それらの弁の障害には大きく分けて、弁が狭くなって流したい方向に流しにくい(①狭窄症)と、弁がうまく閉じずに、流したくない方向に流れていく(②逆流症)があります。
① 狭窄症(きょうさくしょう)
弁が硬くなり、十分に開かなくなることで血流が妨げられる病気です。
- 大動脈弁狭窄症:左心室から大動脈へ血液を送り出す弁が狭くなり、心臓に負担がかかる。
- 僧帽弁狭窄症:左心房から左心室へ流れる血液が妨げられる。
特に大動脈弁狭窄症はさまざまな症状を起こすことがあります。
② 逆流症(ぎゃくりゅうしょう)
弁がしっかり閉じず、心臓が収縮するときに本来は閉めている方向に血液が逆流してしまう病気です。
- 僧帽弁閉鎖不全症:僧帽弁が完全に閉じず、血液が左心房へ逆流する。
- 大動脈弁閉鎖不全症:大動脈弁が完全に閉じず、血液が大動脈から左心室へ逆流する。
それぞれ問題となります。
弁膜症の原因
弁膜症の原因はさまざまですが、主なものは以下の通りです。
- 加齢による変性(弁の硬化や石灰化)
- リウマチ熱の後遺症(細菌感染による炎症)
- 先天的な異常(生まれつき弁の形が異常)
- 感染性心内膜炎(細菌感染による弁の損傷)
リウマチ熱や加齢による変化により、弁が硬くなって狭窄したり、構造が変化してしまい閉鎖不全になります。
また、感染性心内膜炎という弁に菌がつく病気では、その炎症により弁が破壊されることで急激に発症、増悪します。歯科治療後に息苦しさが出てきた。などの人は要注意です。
弁膜症の症状
弁膜症は初期には症状がないことが多いですが、進行すると以下のような症状が現れます。
- 息切れや呼吸困難(特に運動時や横になったとき)
- 動悸や不整脈
- 胸の痛みや圧迫感
- めまいや失神
- 足のむくみや体重増加(心不全の症状)
弁膜症の症状は原因となる弁により違いますが、多くは心臓に負担がかかり、心不全の症状が出ます。また、大動脈弁狭窄症では、うまく全身に血液が行かずにめまいや失神を起こす場合があります。
弁膜症の診断方法
弁膜症は心臓の音や血流の状態を調べることで診断されます。
- 聴診(心雑音の確認)
- 心エコー(超音波検査)(弁の形状や血液の流れを観察)
- 心電図(不整脈や心肥大の有無を確認)
- 胸部X線(心臓の大きさや肺のうっ血を調べる)
- MRI・CT検査(詳細な心臓の構造を評価)
まずは聴診で疑います。疑わしい場合は、心エコーで実際に逆流や狭窄がないかを確認します。実際に心臓に負担がないかは心電図やレントゲン検査等も行います。
弁膜症の治療方法
弁膜症の治療は多岐に渡ります。
① 内科的治療(薬物療法)
まず軽症の場合、薬で心臓の負担をとったりと病状のコントロールを行います。
- 利尿薬(むくみや息切れの軽減)
- β遮断薬(心臓の負担を軽減)
- 降圧薬(ARBなど)
また、病状により使える薬剤や使用を控えた方が良い薬剤もあり、体調や状態を見ながら調整を行います。
② 外科的治療(手術)
重症の場合、手術が必要になることがあります。
- 弁形成術:自分の弁を修復する手術
- 弁置換術:人工弁や生体弁に交換する手術
ただ内服治療や、カテーテル治療と比較して体への負担が大きいため、比較的若い方など手術に耐えられる方が選ばれます。
③ カテーテル治療
手術が難しい高齢の患者さんなどには、カテーテルを用いた治療(TAVIなど)が選択されることがあります。
昔は開胸という胸を開いての手術が必要でしたが、最近はTAVIというカテーテルを用いて人工弁を留置する大動脈弁狭窄症の治療法も確立されて、高齢の方でも治療が可能となりました。
まとめ
弁膜症は進行すると心不全などの重大な合併症を引き起こす可能性があります。息切れなどが出た場合は、弁膜症の可能性があります。早期発見・適切な治療が重要ですので、息切れや動悸などの症状がある場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
【注意】 本記事は一般的な情報提供を目的としており、診断や治療の代わりとなるものではありません。必ず医師の診察を受け、適切な治療を受けることをおすすめします。